
血液浄化器の作用原理
ダイアライザ
(血液浄化器)、ヘモフィルター(血液濾過器)は膜分離技術を応用した血液浄化モジュールである。そこで生じる溶質除去、過剰水分の除去には拡散・濾過の2つの物理的原理を利用している。また溶質が拡散・濾過により膜を透過する際、膜素材との親和性により、一部の溶質が膜に付着(吸着)することもある。拡散
血液などの溶液中で溶質が不均一な状態にある場合、溶質は濃度の濃高い部分から低い部分へ自発的に移動する。この移動現象を拡散
(diffusion)という。
図1
aでは組成の異なるA,B2つの溶液が隔壁を介して存在している。この状態で隔壁を、細孔を有する膜に置き換えたとすると、各溶質とも膜透過しはじめ、やがて図2bのようにA,B中の溶質濃度は等しくなり、2つの溶質は同じ組成になる。この拡散現象の推進力となるものは溶質の濃度さであり、濃度差が大きいほど移動する量は多い。また、いずれの溶質とも最終的に図1bの定常状態に達するが分子サイズ(近似的に分子量)の小さい溶質ほど拡散速度は大きい。拡散係数はその溶液の拡散のしやすさを表す指標で、分子量の増加とともに減少している。また両者の関係は両対数紙上で右下がりの直線傾向がみられることから、次式でみられるべき乗関数で表すことができる。
| D=9.87×10-5(MW)-0.440 |
|
D:溶質の拡散係数(cm2/秒) |
|
MW:溶質の分子量 |
いま図1中の溶液Aを血液、溶液Bを透析液と考える。腎不全患者体内に蓄積する尿素などの蛋白質代謝物、薬物、Kなどの電解質については、透析液濃度を低めもしくは0にすれば、拡散によって血液側から透析液側に移動させる。
(除去する)ことができる。一方、患者に不足しているCa2+,HCO3ーは透析液側濃度を高めに設定することで、拡散により透析側から血液側へ移動させる(補給する)ことが可能となる。この操作を血液、透析液とも図1のようなバッチ(回分)操作でなく、供給・排出を一定速度の連続操作で行えば、高い濃度差を維持しつつ、最大限の溶質の除去、補給ができることになる。これが現用の血液透析で利用している拡散移動である。血液量充填量
(プライミングボリューム)50mlのダイアライザに200mlで血液が流れる場合、50/200=0.25分=15秒が平均滞留時間となる。したがって、わずか15秒間では各溶質の拡散移動は定常状態には達しておらず、血液−透析液間で濃度差が残ったまま、ダイアライザから流出していることになる。この結果、単位時間あたりの除去量は拡散速度の大きい小分子物質ほど多く、分子が大きくなるにつれて少ない結果となる。拡散現象が生じるとき溶媒である水は拡散方向とは逆に、溶質の低濃度側から高濃度側に移動する。これを溶媒の浸透現象という。図
1の例では各溶質に対する浸透流が相殺され、見かけ上、水分は移動していない。通常の血液透析で用いられる透析液も血漿とほぼ等張に作られているため、見かけの浸透流はきわめて小さい場合がほとんどである。血液透析で用いられてる透析膜では、体内に蓄積した老廃物を除去し、
Ca2+,HCO3ーを補給するため、これらの溶質の高い膜透過性が望まれる。一方、患者にとって有用な有形成分、血漿蛋白の大部分を漏出させず、細菌が透析液側から侵入できないようにしなければならない。このようにある溶質成分は透過させ、別のある成分は透過させないような膜を半透膜という。半透膜を用いた拡散移動を透析と呼び、医療で用いられる血液透析とはまったく意味が異なる。すなわち、前者は物理現象についての表現であるのに対し、後者は一治療法を指している。後者には後述の限外濾過による溶質移動も含まれるが、前者には含まれない。前者の透析現象には、溶質の拡散現象とともに、不透過溶質に対する溶媒の浸透現象が逆向きに生じる。血液透析でも血漿蛋白に対する膠質(コロイド)浸透圧が20〜25mmHg程度生じることになるが、透析液の浸透圧を血清浸透圧と同程度にしているので、実際に生じる溶媒の浸透流は少ない。限外濾過
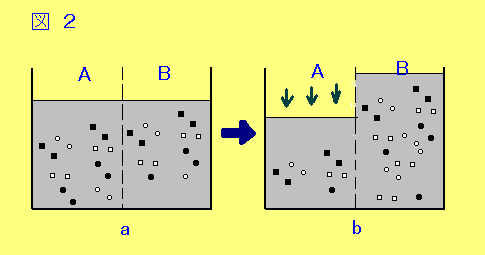
図
2aの状態で溶液Aを押す(陽圧をかける)と、溶液Aの一部が膜を透過し、溶液Bに移動し図2bの状態になる。この現象を濾過といい、圧力差を推進力とする。濾過は図2の溶液Bを引いても(陰圧をかけても)同様に生じるが、浸透圧差が存在しない限り自発的には生じない。血液透析や血液濾過、それらを組み合わせた血液透析濾過といった治療法では、有形成分や血漿蛋白を分離し、それ以下の血漿水成分(血漿から蛋白を除いた成分)を透過させるような限外濾過膜が用いられる。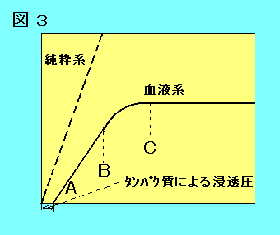
図3は膜間圧力差と透過量の関係を示している。
膜間圧力差とは陽圧、陰圧によって膜の両側に形成された圧力差を意味する。図から明らかなように純水濾過した場合、膜間圧力差に比例した濾過量が得られるのに対し、血液系では、低圧領域でほぼ比例的な濾過量が得られるものの、やがて頭打ちとなり、最終的に最大(限界)値に到達する。したがって、ある膜間圧力差以上に陽圧もしくは陰圧を増しても、もはや濾過量は増えないことを意味している。この理由については通常ゲル分極モデルによって説明される。膜不透過溶質である血漿蛋白はバルク(血液)側膜近傍で、膜濃度分布を濃度分極と呼ぶ。この状態がさらに続くと、やがて溶解度を超えた血漿蛋白が膜面上にゲル化して層をなし、そのとなり(バルク側)に濃度分極層が形成される状態となる。濃度分極層では、圧力差によって膜面方向へ運ばれる蛋白の移動量と濃度分極で形成された濃度差を推進力にした逆拡散蛋白の移動量が釣り合い、透過量はもはや増加しなくなると考えられる。濾過によって膜を透過するのは溶媒の水だけではなく、膜の細孔より小さな溶質も運ばれる。膜の細孔径に溶質径が近づくにつれ、溶質の一部は溶媒である水と一緒に運ばれるものの、残りは膜で阻止されるような現象がみられてくる。この透過の程度を表す指標として、次式などで定義されるふるい係数
(SC)がある。|
SC=CF /CB |
|
CB :バルク(血液)側溶質濃度 |
|
CF :濾液側溶質濃度 |
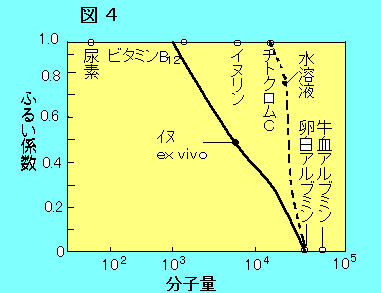
図4はふるい係数と溶質の分子量との関係を表している。この曲線を分画曲線と呼ぶ。水溶液系実験の結果でもシャープな分離が得られてない理由は、膜に均一な細孔が開いておらず、孔径分布が存在するためである。イヌの体外循環実験で分画曲線はさらになだらかになっているが、これはバルク(血液)側近傍に形成された血漿蛋白のゲル層の影響を受けるためである。
|
ポイント |
|
|
拡散 |
濃度差を推進力として生じる。溶質は高濃度側から低濃度側へ移動し、溶媒はその逆方向に移動する。 |
|
限外濾過 |
陽圧(陰圧)によって生じた圧力差を推進力として、溶液成分の一部が膜を透過する現象。 |
|
限外濾過の |
血液濾過の場合、膜非透過成分である血漿蛋白が膜近傍 で濃縮し、濃度分極やゲルを生じて大きな抵抗になる。 |
|
分画曲線 |
溶質の分子量とふるい係数(または反発係数)の関係を表した曲線 。 |